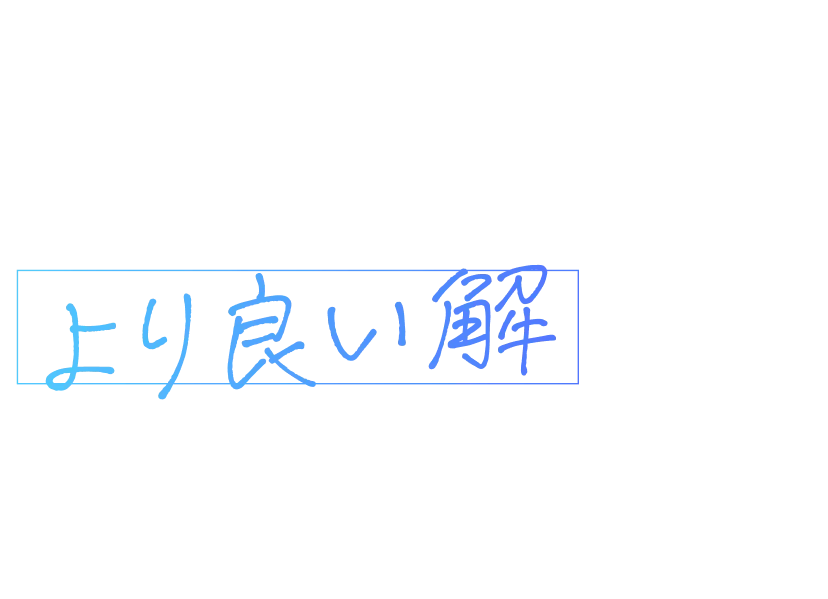








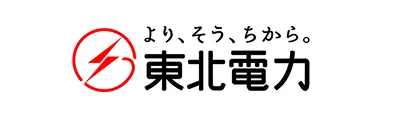
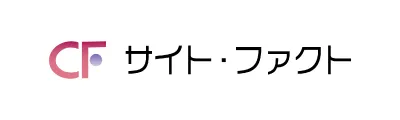


2026.01.27 【登壇セミナー】代表取締役 岸尚希が「GMP管理における生成AI活用入門」の講師を行います。
2026年2月18日(水)、株式会社情報機構が主催するセミナーにおいて、弊社代表取締役CEOの岸尚希が講師を務めることとなりました。 本セミナーのテーマは「GMP管理における生成AI活用入門」です。 近年、急速に進化する生成AI技術ですが、医薬品製造の品質管理(GMP)領域において、具体的にどのように実装し、業務効率化や品質向上につなげていくべきか、その「実践的な活用」への関心が高まっています。 当日は、AI・機械学習の基礎から始まり、製薬業界における最新のAI活用事例、RAG(検索拡張生成)やMCPといった技術的な解決策、そして現場への導入マインドセットまでを網羅的に解説いたします。 また、弊社の製薬品質保証文書業務効率化SaaS「QAI Generator」を用いた具体的な効率化事例や、製薬特化LLMの活用についてもご紹介させていただく予定です。 「生成AIを“使う人”から、GMP領域で実践的に“活かす人”へ」をキーワードに、初学者の方から実務担当者様まで、明日の業務へのヒントをお持ち帰りいただける150分となっております。 皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。 ■ セミナー概要 タイトル: GMP管理における生成AI活用入門 ~AIの基礎・動向・国内外事例・倫理課題とRAG等による解決策・導入へのマインドセット~ 日時: 2026年2月18日(水) 13:00-15:30 開催形式: Zoomオンライン受講(見逃し視聴あり) 講師: 株式会社EQUES 代表取締役 CEO 岸 尚希 ※準備の都合上、開催1営業日前の12:00までにお申込みをお願いいたします。 ■ 講師紹介 株式会社EQUES 代表取締役 CEO 岸 尚希 主経歴等東京大学大学院情報理工学研究科。元松尾研究所プロジェクトマネジャー。松尾研起業クエスト1期生。松尾研究所チーフAIエンジニアとして企業との共同研究に従事。その後、現実世界と情報学の融合を志し、東京大学工学部計数工学科在学時にEQUESを創業。専門および得意な分野・研究システム情報学、特にテラヘルツ波通信とハプティクス(触覚技術)。 ■ 主な講演内容 AI・生成AIの基礎と歴史 製薬業界における国内外のAI活用事例 技術的・倫理的課題とその解決策(RAG、MCP/A2A等) GMP現場におけるAI活用事例(品質・製造・出荷管理) 製薬品質保証SaaS「QAI」のご紹介 ■受講後、習得できること AI・機械学習とはそもそもどういったものなのか、これまでどんな進歩を経てきて今後どのように発展していくのか、を理解することができる 現在のAIの技術レベルで、品質保証の分野を中心に、現場でどのようなことができるようになるのか、活用のイメージを持つことができる AIの今後の発展を踏まえ、将来的にGMP領域における業務をどのような形にしていくべきか、戦略検討の技術面の足がかりを得ることができる ▼ 詳細・お申し込みはこちら(情報機構様Webサイト) 詳細・お申し込みはこちらから
2026.01.19 【無料相談会付き】「きらぼしピッチ特別編 ~松尾研発スタートアップ・AIスタートアップ企業~」に登壇いたします
株式会社EQUESは、2026年1月23日(金)にTokyo Innovation Base (TiB) にて開催される東京きらぼしフィナンシャルグループ主催の「きらぼしピッチ特別編 ~松尾研発スタートアップ・AIスタートアップ企業~」に登壇いたします。 本イベントは、松尾研究所発のスタートアップ企業および注目のAIスタートアップ企業が登壇し、各社の事業内容や最新の取り組みを紹介するピッチイベントです。 当社は「製薬・エネルギー等領域特化型LLMの開発」をテーマに、汎用モデルでは解決できない課題へのアプローチについてお話しさせていただきます。各社ピッチの後は、2時間弱におよぶ個別相談会・名刺交換会もございますので、AI導入にご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。 【イベント概要】 イベント名: きらぼしピッチ特別編 ~松尾研発スタートアップ・AIスタートアップ企業~ 日時: 2026年1月23日(金) 17:00~20:00 会場: Tokyo Innovation Base (TiB) 1階 SQUARE-2 住所: 東京都千代田区丸の内3-8-3(JR有楽町駅 徒歩1分) 主催: 東京きらぼしフィナンシャルグループ / きらぼし銀行 皆様のご来場を心よりお待ちしております。 イベント詳細・お申し込みはこちらから
2026.01.19 【ハンズオンセミナー】製薬・ヘルスケア業界向け「生成AI実践勉強会」を開催いたします
株式会社EQUESは、2026年1月21日(水)にシミックホールディングス株式会社(東京都港区)にて、「松尾研発スタートアップとともに考える製薬・ヘルスケア業界の生成AI実践勉強会」を開催いたします。 本勉強会では、創薬プロセスやヘルスケア領域における生成AIの具体的な活用事例に焦点を当て、単なる解説だけでなく、実践的な導入・活用方法をハンズオンでお伝えいたします。 「生成AIは触っているが、業務には活かしきれていない……」 「AIの、チーム全体の業務フローへの組み込み方がわからない……」 Clinical R&D、PV/PMS、製販業務の現場において、 こうした「個人活用から組織としての活用への壁」に直面されている方は、ぜひご検討ください。松尾研発スタートアップとしての技術的知見を基に、業界特有の課題解決に向けた最適なアプローチをご提案いたします。 「AIで何ができるか」という知識と、 「どう使うか」という実務のノウハウを、一度にお持ち帰りいただける120分です。 【本イベントを通して得られるもの】 悩む時間を最小化する“問いの型” 現場で再現できるAIワークフロー PoC止まりにしない導入ステップ ※ハンズオンセミナーとなりますので、ご自身のPCをお持ちになってご参加ください。※ 【開催概要】 イベント名: 松尾研発スタートアップとともに考える製薬・ヘルスケア業界の生成AI実践勉強会 日時: 2026年1月21日(水) 16:00開始 会場: シミックホールディングス株式会社 本社 (東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA S) 製薬・ヘルスケア業界でDX・AI推進に携わる皆様のご参加をお待ちしております。 イベント詳細・お申し込みはこちらから
Service

EQUESは、高い専門性による創出力を、現場への価値変換力とスピードによって、
シームレスに産業へとつなげることを強みとしています。
EQUESは多くの企業とパートナーシップを結んでいます。 ※一部抜粋
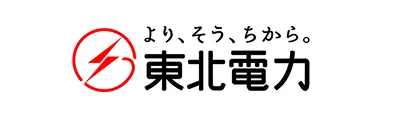








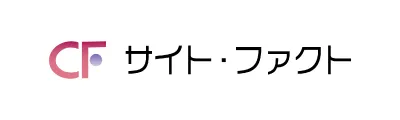


Example

AI×DX寺子屋|茨城県立竜ヶ崎第一高校・附属中学校で「未来の教室」を開催
2025.11.17
中高生が「AIエージェント」で地元企業の課題解決に挑む 株式会社EQUESは、2025年10月18日に茨城県立竜ヶ崎第一高等学校・附属中学校(以下、竜ヶ崎第一高校・附属中学校)で開催された「ホンモノのキャリア教育プログラム」において、「未来を拓くAI×人のチカラ」をテーマにした特別授業を実施しました。本授業は、生徒がAIの現代ビジネスにおける重要性や最先端技術「AIエージェント」について理解を深め、地元企業のリアルな課題解決に挑む、新しい形のAI×ビジネスワークショップとして展開されました。 開催の背景:学校の想いとEQUESの「AI×DX寺子屋」 今回の特別授業は、同校の太田垣校長先生から頂いた「次世代を生きる生徒たちに“ホンモノ”のキャリア教育を提供したい」というご相談がきっかけとなりました。 このご要望に対し、弊社が推進するAI相談サービス「AI×DX寺子屋」のカスタマイズプランを活用。「ビジネスにおけるAIエージェントの台頭」という未来を見据え、AIと“協働”するとはどういうことかを考える、未来創造型のAI×ビジネス授業として実施する運びとなりました。 また、地元企業の実際の課題を題材にすることで、生徒の柔軟な発想が企業に新たな視点をもたらすとともに、生徒自身の地元企業への理解と愛着をも深める、地域全体でのWin-Winな関係構築を目指しました。 【ご協力いただいた地元企業・研究機関様のご紹介(一部:掲載許可を頂いた企業様のみ)】 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 様 株式会社 常陽銀行 様 株式会社タナカ 様 高エネルギー加速器研究機構 様 一誠商事株式会社 様 授業概要:AIエージェントで未来のビジネスをデザインする 当日の授業は、講義とワークショップの二部構成で実施しました。 1. 講義:AIとビジネスの関係 授業前半では、当社スタッフが登壇。EQUESが手掛ける「伴走型技術開発」や「製薬AI事業」などの具体的なAIソリューション事例を紹介するとともに、「なぜ今、ビジネス環境にAIが必要なのか」、そして「AIエージェント」という最先端技術が未来をどう変えるかについて解説しました。AIが単なるツールではなく、ビジネスのあり方そのものを変革する力を持っていることを伝えました。 2. ワークショップ:AIエージェントを活用して地元企業の課題を解決する 後半は、3〜4人のグループに分かれ、「地元企業の課題を分解し、それを解決するAIエージェントを考える」というテーマで実践的なワークショップを実施。生徒たちはAIやPCツールを積極的に活用しながら活発に意見を交換しました。最終的には溢れたアイデアをワークシートにまとめ、教室に設置されたモニターを使って発表を行いました。 (↑写真:常陽銀行様のワークシートの例。生徒は、若者と高齢者など、世代や環境によってサービスを利用したくなる条件は大きく異なっているため、それぞれに合った施策が必要だと考え提案を行いました。) 授業の雰囲気:技術的な質問が飛び交う、ハイレベルな議論 初対面のグループが多い中、すぐに打ち解けて目標に向けた建設的な話し合いが始まり、和気藹々とした雰囲気ながらも白熱した議論が展開されていました。 生徒の皆さんからは沢山の新しい発想が提案され、「アイデアはたくさん出るが、どう企業のサービスと合致させていけばいいのか」などといった発展的な悩みの声が聞かれるなど、その想像力の豊かさには驚かされました。 また、講師陣に寄せられた質問は、「その技術は具体的にどうやって実現するのか?」「ビジネスとしての実現可能性は?」といった、技術的な側面や事業性にまで踏み込むハイレベルなものばかりでした。 (↑写真:講義中の雰囲気。生徒様は熱心に授業に耳を傾け、新しいAIエージェント技術の概要に興味津々でした。) 校長:太田垣先生のコメント 飛ぶ鳥を落とす勢いのAIビジネスから中高生のために貴重なお時間をいただき、心より感謝申し上げます。「AIエージェント」というリクエストに応え、単なる座学ではなく動きながら身に付けるワークショップ型の講座にまとめ上げていただいた情熱と使命感に敬意を表します。準備や進行についても教職員と緻密な調整を重ねていただき、参加した生徒・保護者にも大満足の質の高い講座を一緒に作り上げることができました。 私たち竜一は今後も時代の先頭を走る生徒たちを育てていきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 EQUESより:未来のイノベーターたちへの期待 今回、竜ヶ崎第一高校・附属中学校という非常に意欲的な生徒の皆さんとお会いでき、私たち自身も大きな刺激を受けました。 「AIエージェント」は、まだ社会に普及し始めたばかりの新しい技術です。それを中高生のうちからビジネスの視点で考え、具体的な実現可能性まで踏み込んで質問する生徒たちのポテンシャルに、深く感銘を受けています。 今回の授業が、生徒の皆さんが未来のイノベーターとして羽ばたくための一助となれば幸いです。EQUESは今後も、最先端のAI技術を社会に結ぶ架け橋となる活動を続けてまいります。 今回の授業を実現した「AI×DX寺子屋」について 「AI×DX寺子屋」は、東大生・東大出身者が7割を占めるEQUESのメンバーが、AIやDXに関する素朴な疑問や困りごとをチャットで回答し、お客様のAI活用やDX推進をサポートするサービスです。 AI専門家集団への相談し放題、AIツールの活用提案を特徴とする月額制の「プランA」のほか、今回のようなAI人材研修の実施、技術顧問、開発支援など、お客様の要望に応じて柔軟に内容を決定する「プランB(応相談)」も提供しています。 皆様がAIと歩む未来を創造する一助となれば幸いです。 AI×DX寺子屋の詳細はこちら

SOLIZE PARTNERSが語る、製造業のDXにおけるAI活用のはじめの一歩
2025.10.31
■導入企業の紹介 SOLIZE PARTNERS株式会社(以下SOLIZE PARTNERS)は、日本で初めて3Dプリンターを導入して以来、長年にわたり日本のものづくりを支えているデジタルエンジニアリングのパイオニアです。昨今は社内のデジタルトランスフォーメーション(DX)にも取り組まれており、熟練技術のデジタル化による普及やAIを活用した新しいソリューション開発に注力されています。このたび、株式会社EQUESは、SOLIZE PARTNERSのAI技術導入による課題解決を支援するため、AI PoC(概念実証)サービス『ココロミ』を提供いたしました。導入から運用までの様子をインタビューさせていただきましたので、AI技術導入をお考えの方はぜひご一読ください。 ■SOLIZE PARTNERSの課題 SOLIZE PARTNERSがAI技術の導入において抱えていた課題は、「熟練技術者の頭の中にある情報をどうやってシステム化するか」というものでした。 AIによるDXを進めるにあたって、これまで熟練者が経験によって培ってきた感覚的で言葉にならないノウハウを、いかにAIのシステムに組み込み、活用に漕ぎつけるかという課題は、SOLIZE PARTNERSに限らずものづくり業界全体のDXにおける大きなボトルネックとなっています。 AI導入のプロジェクトを始めるにあたって、この課題を解決するべく、PoC(概念実証)からその分析、アクションプランの策定までを包括的に行う弊社サービス「ココロミ」が導入されました。 ■導入の経緯 「熟練技術者の頭の中にある情報をどうやってシステム化するか」という課題の中で、AIを活用する目的として立ち上がったのが「複数視点からの画像入力を用いた部品特徴の網羅的な検出」というテーマでした。 このテーマを軸に、SOLIZE PARTNERSとEQUESの共同検討がスタートしました。 ココロミを導入する決め手は、弊社が3D生成に関する豊富な経験を有していたことでした。例えば、株式会社セガ様との事業においては、ユーザが簡単なキーワード入力を行うだけでボクセル形式の3Dモンスターを生成するAIを開発した実績があります。(詳しくはこちら)。この開発をSOLIZE PARTNERSに認知していただいたことがご縁となり、共同開発が実現しました。 ■導入後の成果 ココロミでは、以下の2つのテーマでPoC(概念実証)を実施し、それぞれに新たな成果を得ることができました。 取り組み1:設計ナレッジの提案支援 最初の取り組みでは、特定の形状データから特徴を抽出し、それをもとに設計ナレッジを自動で提案するAIの実現性を検証しました。その結果、開発現場で直接活用できるレベルの設計知識をAIが提示できることを確認。従来のように過去資料や文献を検索する手間をかけずに、設計のヒントを得られるようになり、知見の再利用性が大きく高まりました。 取り組み2:3D CADデータの自動生成 次の取り組みでは、自然言語による指示からAIが適切な3D CADデータを生成できるかどうかを検証しました。その結果、単純な形状や構成であればAIによる自動生成が可能であることを確認しました。一方で、複雑な形状を扱う際には、構成部品となる要素データを事前に十分整備しておく必要があることも明らかになり、今後の改善の方向性が見えてきました。これらの検証を通じて得られた成果は、SOLIZE PARTNERSにおけるAI活用を現場レベルへ展開するための第一歩となりました。 ■ココロミ導入を通しての感想 ココロミの推進において、EQUESの徹底した伴走が大きな安心感につながったとのお言葉をいただきました。開発中、多くの技術的懸念や疑問に対し、担当PMエンジニアが都度、論理的な裏付けをもって丁寧に説明させていただきました。技術的な不確実性のあるテーマであったからこそ、一貫した伴走と安心感が、『ココロミ』の提供価値を高め、開発を成功に導くための心の支えとなったと評価いただいています。 さらに、AIという新しい技術への挑戦は、社内への新しい風となり、社員の意識を新たにする理由に繋がりました。 単なる技術検証に留まらず、AI活用に対する社内全体の意識を変革するという、文化的な成果も生まれました。 ■今後の展望 今回の『ココロミ』を通じて得られた知見と信頼関係を基に、SOLIZE PARTNERSはAI技術の応用をさらに深化させていく意向を示されています。 SOLIZE PARTNERS側の担当者様は、「ぜひ次の取り組みをやりたい」と力強く語り、自社の取り組みを継続していく決意を表明されました。 そして、今後の重要なテーマの一つとして、XAIの必要性が挙げられました。 (XAIとは…「説明可能なAI(Explainable AI)」の略。AI、特にディープラーニングは、なぜその結論に至ったのかという判断プロセスが複雑で、人間には理解しにくい「ブラックボックス」状態になることがある。XAIは、このブラックボックスの中身に説明を与え、AIの判断根拠や理由を人間が理解できる形で示すための技術やその研究分野を指す。AIの信頼性と透明性を高め、医療や金融、自動運転など、高い安全性が求められる分野で公正に活用されることを目指している。) SOLIZE PARTNERS側の担当者様は、「ブラックボックスになってしまいがちなAIの判断に説明の有無があることで、現場での意思決定に使えるかどうかは大きく変わる」と、実務における説明責任の重要性を強調されました。 株式会社EQUESは、『ココロミ』を通じて培われた具体的な知見と技術的な基盤をもとに、SOLIZE PARTNERSの新たな価値創造と産業の高度化を引き続き力強く支援してまいります。 SOLIZE PARTNERS HPにて、弊社CEO岸および本プロジェクトPMの村山のインタビューが掲載されております。詳しくはこちらからご覧ください。
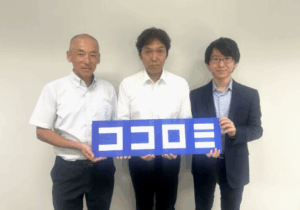
AI-OCRで製造現場の記録を自動化|Cyto-Factoの導入事例
2025.10.23
―導入した会社の紹介 Cyto-Facto(サイトファクト)は、神戸に拠点を置く細胞・遺伝子治療分野に特化したCDMO企業です。FBRIの細胞治療研究開発センターを継承し、PIC/S GMP準拠の製造体制を整備。開発から製造、品質試験まで一貫支援し、独自のシステムによるDX推進で、安全かつ高品質な先端治療の社会実装を目指しています。 ― 今回のプロジェクトを始められた背景について教えてください。 製造現場では、通信機能のない機器が多く残っており、液晶パネルや制御PCの画面に表示される情報を作業員が手作業で記録していました。従来のOCR技術では操作が難しい上、読み取り精度も不安定で、業務効率化には限界があったのです。そこで私たちは、AI-OCR技術を活用し、画像認識とデータ抽出の精度向上を目指すプロジェクトを立ち上げました。 ― 具体的にはどのような取り組みをされたのでしょうか? まず、液晶パネルや制御PC画面から取得した画像データをAI-OCRで読み取り、MESやLIMSへ自動入力する仕組みを検討しました。さらに、UIモック版やクラウド版のOCRシステムを開発し、音声入力によるデータ修正機能(日本語・英語対応)も実装しています。また、GMP/GCTP規制を考慮したインターフェース設計にも取り組みました。 ― 開発パートナーにEQUESを選ばれた理由は何ですか? EQUES様は高精度AI-OCR技術の開発実績を持ち、医療や製造分野でのGMP対応経験が豊富でした。また、オフライン環境でのOCR対応力やMES/LIMSとの連携を見据えた提案力・技術力も魅力的でした。複数の課題に対し具体的な解決策を提示していただいたことも大きな決め手です。 ― これまでにどのような成果が得られていますか? UIモック版OCRの社内動作を確認済みで、音声入力によるデータ修正機能のデモも実施しました(日本語・英語対応)。さらに、GPTモデルを活用したクラウド版OCRの開発も進行中です。サンプル画像では100%の認識精度を達成しており、GMP対応を見据えた修正履歴管理機能の設計にも着手しています。 ― 現場からの反応はいかがでしょうか? 「計画通りに開発が進んでいる」「進捗共有がタイムリーで非常にスムーズ」「本開発に向けた準備が円滑に進んだ」といった声が多く寄せられています。現場にとっても大きな期待感につながっていると感じています。 ― 今後の展望を教えてください。 今後は、GMP/GCTP対応を含めたインターフェース設計の詳細化を進めていきます。さらに、iOSやAndroidに対応したアプリの開発や、動画・動的テロップの認識といった新たな機能拡張にも取り組んでいく予定です。
Member

東京大学大学院.ex 松尾研プロジェクトマネジャー.
松尾研起業クエスト1期生.
松尾研チーフAIエンジニアとして企業との共同研究に従事.その後,現実世界と情報学の融合を志し,計数工学科在学時にEQUESを創業.専門はシステム情報学,特にテラヘルツ波通信とハプティクス(触覚技術).

東京大学大学院. ex 松尾研プロジェクトマネジャー
松尾研起業クエスト2期生.産総研「覚醒」事業採択.
AIビジネスコンテスト全国優勝後,計数工学科で現CEO岸と出会いEQUESを創業.
専門は数理情報学であり,クラスタリング最適化や医療AI分野の研究でトップジャーナルや国際会議に採択されている.

Advisor
松尾 豊
技術顧問
2007年より,東京大学大学院工学系研究科准教授. 2019年より教授. 専門分野は,人工知能,深層学習,ウェブマイニング. 人工知能学会からは論文賞(2002年),創立20周年記念事業賞(2006年),現場イノベーション賞(2011年),功労賞(2013年)の各賞を受賞. 2020-2022年,人工知能学会,情報処理学会理事. 2017年より日本ディープラーニング協会理事長. 2019年よりソフトバンクグループ社外取締役. 2021年より新しい資本主義実現会議 有識者構成員. 2023年よりAI戦略会議座長.
Column

医療AIの活用例とメリット!生成AIやSaMDで実現する病院経営の効率化
2026.01.20
「医師の働き方改革への対応が急務だが、人手不足で現場は限界だ」 「医療の質を上げつつ、経営の効率化も図りたい」 病院経営に携わる皆様は、このような深い悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。日々の診療業務に追われながら、新しい技術の導入を検討するのは容易なことではありません。 しかし、現在急速に進化している「医療AI」は、こうした医療現場の課題を解決する強力なパートナーとなりつつあります。画像診断による見落とし防止や、生成AIによるカルテ作成の自動化など、AIは医師の負担を減らし、患者様に向き合う時間を創出します。 この記事では、医療AIの基礎から最新の活用事例、メリット・デメリット、そして具体的な導入手順までをわかりやすく解説します。読み終える頃には、自院に最適なAI活用のイメージが湧き、次の一歩を踏み出すための道筋が見えているはずです。 医療AIとは?基本概念と2026年のトレンド 医療AI(人工知能)とは、医療現場における診断支援、治療方針の決定、業務効率化など様々な分野でサポートするAI技術のことです。近年、法整備も進み、AIを活用したプログラムは「プログラム医療機器(SaMD)」として承認されるケースが増えています。 医療AIの進化と現状 かつては研究段階だったAIも、現在では実用段階に入っています。特に2024年から2025年にかけては、従来の画像診断アシストに加え、「生成AI」の活用が急速に広がっています。生成AIとは、テキスト、画像、音声、動画などの新しいコンテンツを自動で生成できる人工知能のことです。医療現場では、自然言語処理技術を用いて、医師のカルテ作成支援や、患者様への説明資料の要約など、これまで人間が手作業で行っていた事務作業を大幅に効率化できる可能性を秘めています。 なぜ今、医療AIが必要なのか 背景には、少子高齢化による医療需要の増加と、医師の労働時間短縮(働き方改革)という社会的課題があります。限られた医療リソースで質の高い医療を提供し続けるためには、AIによる業務の効率化と高度化が不可欠となっています。 医療AIの代表的な活用例 具体的に、医療現場でAIがどのように使われているのか、代表的な事例をご紹介します。 1. 画像診断支援(AI画像診断) 最も普及が進んでいる分野の一つです。X線、CT、MRIなどの画像をAIが解析し、がんや病変の疑いがある箇所を自動でマーキングします。医師の「第2の目」として機能することで、見落としを防ぎ、診断の精度向上に貢献しています。 2. 生成AIによる業務効率化 生成AIを活用し、問診票の内容からカルテの下書きを自動作成したり、紹介状や返書の作成をサポートしたりするシステムが登場しています。これにより、医師が事務作業に費やす時間を大幅に削減し、本来の診療業務に集中できる環境を作ります。 3. 創薬・ゲノム医療 製薬や研究分野でもAIは活躍しています。膨大な論文データや遺伝子情報をAIが解析し、新薬の候補物質を見つけ出したり、患者様一人ひとりのゲノムデータに合わせた「個別化医療」の提案を行ったりしています。また、弊社EQUESでも、製薬分野における文書業務を効率化する「QAI Generator」を提供しており、専門的な書類作成時間を大幅に(70%)短縮した実績があります。 病院のAI導入について詳しく書いた記事もございますので、こちらもぜひご一読ください。 2026年注目キーワード:SaMD(プログラム医療機器)とは? 医療AIについて調べる中で、「SaMD(サムディー)」という言葉を目にする機会が増えているかもしれません。これは Software as a Medical Device の略で、日本語では「プログラム医療機器」と呼ばれます。 2026年の医療トレンドを語る上で欠かせないこの言葉について、基本からわかりやすく解説します。 「ソフトそのもの」が医療機器になる時代 これまで医療機器といえば、MRIやCTスキャナー、ペースメーカーといった「ハードウェア(機械)」を指すのが一般的でした。しかし、SaMDはそれらとは異なり、インストールされたソフトウェア(プログラム)自体が医療機器として認められたものを指します。 SiMD(Software in a Medical Device): 従来の医療機器に組み込まれているソフト。機械と一体で機能する。 SaMD(Software as a Medical Device): スマートフォンやPC上のアプリ、クラウド上のAIなど、ソフト単体で機能する。 つまり、手元のスマートフォンやタブレットが、アプリを入れることで「診断や治療を行う医療機器」に変わる可能性があるのです。 SaMDの主な2つの種類 SaMDは大きく分けて、診断を助けるものと、治療に使うものがあります。 診断支援(AI診断など): CTやレントゲン画像をAIが解析し、医師に「ここに病変の疑いがあります」と提示するシステムです。多くの医療AIはこのカテゴリーに含まれます。 治療用アプリ(DTx: デジタルセラピューティクス): 患者様が自身のスマホに入れて使用するアプリです。例えば、ニコチン依存症や高血圧症の治療において、日々の行動変容を促すことで治療効果を上げるものが実用化されています。 医療AIとSaMDの深い関係 「医療AI」と「SaMD」は混同されがちですが、関係性としては「SaMD(プログラム医療機器)という枠組みの中で、AI技術や生成AIが使われていることが多い」と理解するとスムーズです。 特に2024年から2025年にかけては、承認プロセスの効率化(二段階承認など)も議論されており、最新のAI技術を搭載したSaMDが、より早く現場に届くようになることが期待されています。 ハードウェアの買い替えを待たず、ソフトウェアのアップデートだけで最新の診断機能を利用できる点は、病院経営においてもコストメリットにつながる重要なポイントと言えるでしょう。 一方で、事務作業支援(議事録作成)AIなどといった、診断や治療を直接行わない医療AIは、SaMDの承認が不要なケースが多いです。AI導入を進めるにあたって、ハードルが低く比較的取り組みやすいものとなっております。 AI医療のメリットとデメリット・リスク AI導入には大きなメリットがある一方で、注意すべきリスクも存在します。これらを正しく理解することが成功の鍵です。 医療AIのメリット 業務効率化と負担軽減: 事務作業や単純作業を自動化し、医療従事者の長時間労働を是正します。 診断精度の向上: 人間の目では判別が難しい微細な病変の発見を支援し、誤診リスクを低減します。 医療の均てん化: 専門医が不在の地域や時間帯でも、AIの支援により一定レベルの診断品質を担保しやすくなります。 医療AIの課題・デメリット・リスク ハルシネーション(もっともらしい嘘): 生成AIは、事実と異なる情報を生成する可能性があります。最終的な診断や判断は、必ず医師が行う必要があります。 セキュリティとプライバシー: 患者様の機密性の高い個人情報を扱うため、万全のセキュリティ対策が求められます。 責任の所在: AIが誤った判断をした場合の責任の所在について、法的な議論やガイドラインの理解が必要です。あくまでAIは「支援ツール」であり、責任主体は医師にあるという原則を忘れてはいけません。 医療AI導入のステップと成功のポイント 「何から始めればいいかわからない」という方のために、導入の基本的な流れを解説します。 ステップ1:課題の明確化と目的設定 まずは、自院のどの業務に課題があるのかを洗い出します。「画像診断の待ち時間を減らしたい」「カルテ作成の残業を減らしたい」など、具体的な目的を定めることが重要です。 ステップ2:情報収集とパートナー選定 目的に合ったAIサービスや開発会社を探します。国内には富士通やNECといった大手企業のほか、特定の領域に特化したベンチャー企業も多数存在します。 弊社EQUESは、東京大学松尾研究所発のAIスタートアップとして、AIを用いた「伴走型技術開発」を得意としています。パッケージ製品の導入だけでなく、「自院の課題に合わせたAI活用を相談したい」というニーズにも、専門家集団がお応えします。 ステップ3:PoC(概念実証)とスモールスタート いきなり全科に導入するのではなく、特定の診療科や部門で小規模にテスト導入(PoC)を行います。現場のスタッフの使い勝手や、実際の精度を確認し、運用ルールを固めてから本格導入へ進みます。弊社では、このPoCを月額250万円から実施できる「ココロミ」プランもご用意しています。 まとめ 医療AIは、医師不足や過重労働といった医療現場の課題を解決する大きな可能性を秘めています。画像診断から生成AIによる事務効率化まで、その活用範囲は日々広がっています。 本記事の要約 医療AIは「SaMD:プログラム医療機器」として実用段階にあり、2025年は生成AI活用がトレンド。 画像診断支援やカルテ作成自動化などにより、診断精度の向上と業務効率化が実現できる。 ハルシネーションやセキュリティなどのリスクを理解し、医師が最終判断を行う体制が不可欠。 導入は課題の明確化から始め、信頼できるパートナーと共にスモールスタートで進めるのが成功の鍵。 AI導入は決して難しいものではありません。まずは「こんなことはできないか?」という現場の小さな疑問から始めてみてはいかがでしょうか。 株式会社EQUESでは、AIに関するお悩みを月額10万円からAI専門家に相談し放題の「AIDX寺子屋」などのサービスを通じて、医療機関様のAI活用を全力でサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせはこちら

ジェネレーティブデザインとは?AIの活用や製造業の事例・メリットを徹底解説
2026.01.20
「もっと軽量で、かつ強度の高い部品を設計したい」 「従来のアイデアにとらわれない、新しい形状を生み出したい」 日々、設計や開発の現場でこのような課題に直面している技術者やプロダクトマネージャーの方は多いのではないでしょうか。これまでの設計プロセスでは、人間の経験や勘に頼る部分が大きく、工数もかかる上に、アイデアの幅にも限界がありました。 そこで今、世界中の製造業で注目を集めているのが「ジェネレーティブデザイン」です。この技術を活用することで、AIが数千もの設計案を自動で生成し、設計業務を劇的に効率化できるだけでなく、人間には思いつかないような革新的なデザインを手に入れることが可能になります。 この記事では、ジェネレーティブデザインの基礎知識から、「生成AI」との関連性、トポロジー最適化との明確な違い、そしてトヨタやNASAなどの具体的な導入事例までをわかりやすく解説します。読み終える頃には、自社の開発にどのようにこの技術を取り入れるべきか、具体的なイメージを持っていただけるはずです。 AI導入の無料相談はこちらから ジェネレーティブデザインとは? 仕組みと基本概念 ジェネレーティブデザイン(Generative Design)とは、設計者が入力した「条件」に基づいて、コンピュータ(AI)が膨大な数の設計案を自動的に生成する、新しい設計手法のことです。 AIが最適な形状を「探索」する 従来の設計(CAD)が、設計者の頭の中にある形状をコンピュータ上に「清書」する作業だったのに対し、ジェネレーティブデザインは、設計者が「ゴール(目標)」と「制約条件」を提示することから始まります。 例えば、「重量を〇〇kg以下にする」「耐荷重は〇〇kg以上」「材料はアルミニウム」「製造方法は3Dプリント」といった条件を入力します。すると、AIがクラウドコンピューティングのパワーを使い、進化論のように何千通りものシミュレーションを並列で行います。設計者はその中から、最もバランスの良い最適な案(トレードオフを考慮した解)を選ぶだけです。 【比較表】トポロジー最適化との決定的違い よく混同される技術に「トポロジー最適化」がありますが、両者には明確な違いがあります。 特徴トポロジー最適化ジェネレーティブデザインスタート地点既存の形状あり(基本設計から不要な部分を削る)形状なし(ゼロベース)(条件のみから形状を生成)目的特定の形状の「改善・軽量化」未知の「最適解の発見・多案比較」生成される案基本的に1つ(最適解のみ)数百〜数千の選択肢形状の特徴元の形状の面影が残る有機的で生物のような形状になりやすい ジェネレーティブデザインは、人間が想像もしなかったような有機的な形状(骨や網のような形)をゼロから生み出せる点が最大の特徴です。 ジェネレーティブデザインと生成AIの関係 近年話題の「生成AI(Generative AI)」とジェネレーティブデザインは、言葉は似ていますが、指している範囲や役割が異なります。 生成AI(Generative AI):ChatGPTやMidjourneyのように、学習データをもとに新しい「テキスト、画像、音声」などを生成するAI全般を指します。製造業では、マニュアル作成や議事録要約、アイデア出しの壁打ちなどに使われます。 ジェネレーティブデザイン:物理法則(強度計算や流体解析など)に基づき、工学的に成立する3Dモデルを生成する「具体的なエンジニアリング手法」です。 現在は、ジェネレーティブデザインを生成AIが補助するサービス設計が進んでいます。例えば、PTC社の「Creo」やAutodesk社の「Fusion 360」、Siemens社の「NX」といったツールでは、AIが過去の設計データを学習し、より人間に近い、あるいは人間を超越した設計提案を行う「AI設計アシスタント」としての機能が強化されています。 生成AIのCAD活用ツールを詳しく紹介した記事もございますので、ご興味をお持ちの方はこちらもご一読ください。 なぜ今、注目されているのか? 製造業でのメリットと事例 ジェネレーティブデザインが単なる「設計支援ツール」の枠を超え、製造業の経営課題を解決する手段として注目されているのには、大きく4つの理由があります。 1. 劇的な「軽量化」と「材料コスト」の削減 最も分かりやすいメリットは、極限まで無駄を削ぎ落とした軽量化です。 必要な強度や耐久性をAIが計算し尽くして形状を決めるため、人間が安全マージンをとって厚く設計していた部分を、科学的根拠に基づいて薄く、軽くできます。これは、自動車や航空機などの燃費向上に直結するだけでなく、原材料費(マテリアルコスト)の直接的な削減にも繋がります 。 2. 部品統合による「製造・管理コスト」の圧縮 複数の部品をボルトや溶接で組み合わせていたユニットを、ジェネレーティブデザインなら「ひとつの複雑な部品」として一体的に設計・製造できます。 これにより、組み立て工数が減るだけでなく、部品点数が減ることで在庫管理や発注業務といった間接コストまで大幅に圧縮することが可能です。これは製造業全体のサプライチェーン効率化に貢献します 。 3. 開発リードタイムの短縮と「手戻り」の防止 従来、設計案を一つ作るのには数日〜数週間かかり、解析(CAE)でNGが出れば最初からやり直し……という「手戻り」が頻発していました。 ジェネレーティブデザインでは、設計の初期段階で「製造要件(3Dプリンタか、切削か)」や「強度要件」をインプットし、AIがそれをクリアした案だけを数千通り提示します。つまり、「作れないもの」「壊れるもの」が最初から除外されるため、開発期間を劇的に短縮できるのです 。 4. 技術者の「バイアス」打破とイノベーション 熟練の設計者ほど、「この部品はこういう形であるべきだ」という経験則(バイアス)に縛られがちです。 AIにはそのような先入観がありません。物理法則だけに従って解を導き出すため、人間では思いつかないような独創的な形状や、性能を飛躍的に高めるアイデアを発見できます。これは、製品の付加価値を高め、競合他社との差別化を図るための強力な武器になります 。 導入事例:世界と日本の先端事例 実際に上記のような成果を出している企業の取り組みを見てみましょう。 トヨタ自動車(シートフレーム・ECU):自動車のシートフレームの設計に導入し、軽量化と薄型化を実現して車内空間を拡大しました。また、電子制御ユニット(ECU)の設計では、放熱性能と軽量化を両立する形状をAIで探索し、最適化を図っています。 (参考元:Toyota's generative design seat frame uses next-level AI、軽量化のその先へ: デンソーによる先進的 ECU のデザイン) NASA(惑星探査機・望遠鏡):木星の衛星へ送る着陸船の設計において、ジェネレーティブデザインを活用。従来の手法よりも30%の軽量化に成功しました。また、宇宙望遠鏡の部品では、10個以上のパーツを「1つ」に統合し、組み立ての手間とリスクを大幅に減らしています。 (参考元:NASA's evolved structures use generative design to fuel new space missions、GAMMA: Space Exploration Lander) ゼネラルモーターズ(GM):シートベルトを固定するブラケットを再設計し、8つの部品を1つに統合。強度は20%向上し、重量は40%軽量化しました。 (参考元:General Motors | Generative Design in Car Manufacturing) 導入へのステップと「失敗しない」ためのポイント 「素晴らしい技術だが、導入ハードルが高いのでは?」と感じる方もいるかもしれません。安心してください。一つひとつステップを辿れば低リスクで着実な導入を目指すことが可能です。 導入のステップ 目的の明確化: どの部品を、何のために(軽量化?コストダウン?納期短縮?)改善したいかを定めます。 ツールの選定: 自社のCAD環境や製造要件(3Dプリンタか切削か)に合わせて、Autodesk Fusion 360, PTC Creo, Siemens NXなどを検討します。 PoC(概念実証): 小さなプロジェクトで試験的に運用し、効果を検証します。 ツール選定について詳しく書いた記事もございますので詳しくはこちらをご覧ください。 よくある課題:AI設計と製造現場のギャップ 多くの企業が直面するのが、「AIが出した形状を実際の製造(加工)に落とし込めない」という課題です。ジェネレーティブデザインは、3Dプリンター(アディティブ・マニュファクチャリング)を前提とした複雑な形状を出すことが多いため、自社の既存設備(切削や鋳造)で製造可能な形状に制約条件を設定するノウハウが必要です。 AI導入の「壁」を乗り越えるために ジェネレーティブデザインを含め、AI技術を自社の設計プロセスに組み込むには、単なるソフトの購入だけでなく、「自社に合わせたカスタマイズ」や「運用サポート」が不可欠です。 弊社、株式会社EQUES(エクエス)は、東京大学松尾研究所発のスタートアップ企業として、AI技術を用いた「伴走型技術開発」を行っています。 (2026年1月現在)AIによる3D CAD生成ソフトを研究開発中の弊社は、多くの製造業の方々からご依頼をいただいた経験があり、製造業の発展に貢献すべく日々研究開発に勤しんでおります。 AI×3D CADについて詳しくはこちら↓ AIの無料相談はこちらから 大規模開発の前に「ココロミ」で検証を AI導入で失敗しないためには、いきなり大規模なシステムを入れるのではなく、まずはPoC(概念実証)を行うことが重要です。 弊社の生成AIPoCパッケージ「ココロミ」は、月々250万円からのスタンダードプランで、貴社の課題に合わせたAI活用の検証をスピーディに行います。設計データの分析や、AIによる業務効率化の可能性を、リスクを抑えて確認いただけます。 「AI×DX寺子屋」で専門家に相談 「まずは何から始めればいいかわからない」「ジェネレーティブデザインの理論的な部分を知りたい」という場合は、「AI×DX寺子屋」をご活用ください。東大出身のAI専門家集団が、チャットで技術的なお困りごとを解決します。 月額20万円でチャット相談し放題のプランもあり、社内の技術顧問のような感覚で、大学レベルの専門知識を現場に取り入れることができます。 製薬分野や製造業におけるAI活用、SaaS開発の実績も豊富なEQUESが、貴社のジェネレーティブデザイン導入やAI活用を全力でサポートいたします。 まとめ ジェネレーティブデザインは、製造業の常識を覆す可能性を秘めた技術です。 ジェネレーティブデザインとは: ゴールと条件を入れれば、AIが数千の最適解を生成してくれる技術。 メリット: 大幅な軽量化、部品統合によるコスト削減、NASAやトヨタも採用する革新性。 成功の鍵: トポロジー最適化との違いを理解し、適切なPoC(検証)を経て現場に導入すること。 「設計プロセスを革新したい」「AIを活用して競合他社に差をつけたい」とお考えの方は、ぜひ一度EQUESへご相談ください。AIのプロフェッショナルが、貴社の技術開発を伴走支援いたします。 AIの無料相談はこちらから

GMP文書とは?AIで作成・管理を効率化する製薬品質保証の新しい方法
2025.12.12
製薬業界における品質保証の現場で、「GMP文書」の作成や管理に多くの時間を費やされている方も少なくないのではないでしょうか。度重なる改訂作業、レビューの往復、そして査察への備えなど、その業務は膨大で、ヒューマンエラーのリスクも常につきまといます。求められる品質基準は年々高まる一方で、リソースは限られている、そんなジレンマを抱えているかもしれません。 この記事では、医薬品の品質を守るために不可欠なGMP文書の基礎知識から多くの品質保証(QA)部門が直面している具体的な課題、そしてそれらの課題をAIの力でどのように解決できるのかまでを分かりやすく整理します。 この記事を読み終える頃には、GMP文書管理の現状を打開するヒントが見つかり、業務効率化に向けた新たな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。 弊社(株式会社EQUES)は、製薬分野に強く、経済産業省のGENIACにも採択されたGMP文書業務効率化SaaS「QAI Generator」サービスを展開しております。事例集もございますのでぜひご活用ください。 製薬DX事例集はこちらから 製薬DXに関する無料相談はこちらから GMP文書とは?その重要性と基本を解説 GMP文書について理解を深めるために、まずはその土台となる「GMP」そのものについて確認しておきましょう。 GMPとは?医薬品の品質を守るルール GMPとは「Good Manufacturing Practice」の略語で、日本語では「製造管理及び品質管理の基準」と表現されます。中でも医薬品に関わるGMPのことを医薬品GMPと呼びます。 医薬品は、人の健康や生命に直接影響を与えるものです。そのため、万が一にも品質に問題があってはなりません。医薬品GMPの目的は、製造過程での人為的な誤りを最小限にすること、医薬品の汚染や品質低下を防ぐこと、そして常に高い品質を保証するシステムを設計することにあります。 このGMPの基準は、厚生労働省令(「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」)が定めており、一般に「GMP省令」と呼ばれています。 GMP文書の役割と法的な位置づけ GMP省令では、このGMPを確実に実行するために、いわゆる「GMPの三原則」が基本理念として示されています。 人為的ミスの防止 医薬品の汚染および品質低下の防止 高い品質を保つ仕組みづくり これらの原則を実現するために不可欠なのが「文書化」です。GMP省令では、製造所の職員の責務や管理体制を文書によって適切に定めること や、作業手順を文書化してマニュアル通りに作業させ、それを記録することが求められています。 つまりGMP文書とは、GMP省令という法律に基づき、医薬品の品質を保証する仕組みを構築し、その仕組み通りに業務が実行されたことを証明するために作成・管理される、すべての文書と記録のことを指します。 医薬品GMP文書にはどんな種類がある?主な文書と管理プロセス 医薬品GMP文書と一口に言っても、その種類は多岐にわたります。これらは大きく4つのカテゴリーに分類することができます。 主な医薬品GMP文書の種類(基準書、手順書、記録書など) GMP省令で要求される文書は、主に以下の4つに分けられます。 製品標準書 医薬品の品目ごとに、製造承認された内容や製造手順、品質規格、試験方法などをまとめた、その製品の「憲法」とも言える文書です。 基準書 製造所全体で守るべき基本的なルールを定めた文書です。 (例)衛生管理基準書、製造管理基準書、品質管理基準書 手順書 (SOP: Standard Operating Procedures) 基準書に基づき、個々の作業や業務を「誰が、いつ、どのように行うか」を具体的に定めた文書です。 (例)変更の管理に関する手順書、逸脱の管理に関する手順書、自己点検に関する手順書、教育訓練に関する手順書、文書及び記録の管理に関する手順書など、非常に多くの種類があります。 記録書 手順書に基づいて作業や試験を実施した結果を記録する文書です。作業が正しく行われたことを証明する「証拠」となります。 (例)製造指図書に基づく製造記録、試験検査記録、変更申請書(変更記録)、自己点検記録、教育訓練記録 医薬品GMP文書の作成・承認・保管・改訂のライフサイクル これらの医薬品GMP文書は、一度作成したら終わりではありません。常に最新かつ最適な状態を保つために、一連のライフサイクル(作成→承認→配布・教育→実行→保管→改訂→廃棄)に沿って適切に管理される必要があります。 特に保管については、例えば記録書は作成日から5年間(ただし有効期間+ 1年が5年より長い場合はその期間)の保管の義務(GMP省令第20条より)など、厳格なルールが定められています。 多くの企業が抱えるGMP文書管理の課題 GMP文書は医薬品の品質保証の根幹ですが、その管理には多くの課題が伴います。特に従来の紙ベースや手作業での運用では、以下のような問題が発生しがちです。 作成・レビューにかかる膨大な時間と人的コスト GMP文書の作成、特にSOP(手順書)の新規作成や改訂には、多くの時間と労力が必要です。さらに、作成された文書は複数の部門や担当者によるレビューと承認を経る必要があり、このプロセスが長期化することも少なくありません。手書きやExcelでの文書作成は、時間がかかるだけでなく、貴重な専門人材のリソースを圧迫する大きな要因となっています。 整合性の担保とヒューマンエラーのリスク GMP文書は、製品標準書を頂点として、基準書、手順書、記録書が互いに関連し合っています。紙ベースの管理では、一つの文書を改訂した際に、関連する他の文書への反映が漏れてしまう「不整合」のリスクがあります。 また、「用語の表記ゆれ」、旧版の文書を誤って参照してしまう、あるいは手書きによる記載ミスや読み間違い といったヒューマンエラーも起こりやすくなります。 査察対応とデータインテグリティの課題 当局による査察(ささつ)の際には、要求された文書や記録を迅速に提示する必要があります。しかし、紙の文書が書庫に膨大に保管されている場合、必要な文書をすぐに探し出すのは困難です。また、文書の紛失や劣化のリスク も伴います。 近年重視されている「データインテグリティ(データの完全性・正確性・信頼性)」の観点からも、手書きの記録は「いつ誰が変更したか」の追跡が難しく、データの信頼性を担保しにくいという課題があります。 薬機法の改正による規制の厳格化 2025年に施行された改正薬機法では、MAH(製造販売業者)による製造所の管理監督責任がより一層強化され、製造業者自身のGMP省令遵守も薬機法上で直接義務化されるなど、規制は厳格化しています。 PMDA(医薬品医療機器総合機構)においても、2025年4月から「医薬品品質管理部」に検定・検査課が新設されるなど、適合性調査(査察)の体制が強化されています。こうした背景から、査察や監査に対する文書管理の重要性は、ますます高まっていると言えるでしょう。 (参考元: 2024年度 GMP / GCTP Annual Report) AIで変えるGMP文書業務の未来 - QAI Generatorのご紹介 こうしたGMP文書に関する根深い課題を解決する鍵として、今、AI(人工知能)の活用が注目されています。 AI活用がGMP文書業務にもたらす変革 AI、特に文章生成を得意とするAI技術は、GMP文書の作成・管理プロセスを劇的に変える可能性を秘めています。 例えば、膨大な時間がかかっていた文書の新規作成や改訂案の作成をAIがサポートすることで、担当者はより専門的な判断やレビュー業務に集中できます。また、AIによるチェック機能は、表記ゆれや参照漏れといったヒューマンエラーの防止にも貢献します。 EQUESの「QAI Generator」とは? 弊社、株式会社EQUESは、東京大学松尾研究所発のベンチャーとして、AIを用いた「伴走型技術開発」で企業様をサポートしております。特に強みを持つ製薬分野において、GMP文書業務の課題を解決するために開発したのが、製薬品質保証のGMP文書業務効率化SaaS「QAI Generator」です。 「QAI Generator」は、難解な操作を必要としません。簡単な質問に答えていくだけで、必要な書類や法務書類をAIが自動で作成します。 「QAI Generator」が実現する具体的な業務効率化 「QAI Generator」の導入により、GMP文書業務の効率は飛躍的に向上します。実際に導入いただいた企業様では、文章の作成時間が5割カットされ、さらにレビュー時間も7割以上短縮されたという実績が報告されています。 これは、AIがたたき台を作成することで「ゼロから書く」負担をなくし、同時に表記ゆれや形式の不備を減らすことで、レビューの手戻りを大幅に削減できるためです。 「QAI Generator」は、経済産業省のGENIACにも採択されており、その技術と将来性が高く評価されています。 GMP文書ツール導入で失敗しないためのポイント AI活用を含め、GMP文書の管理ツールを導入する際には、いくつかの重要なポイントがあります。 自社の課題とツールの機能がマッチしているか まずは、自社が抱える最大の課題がどこにあるのかを明確にすることが重要です。「文書の作成時間を短縮したいのか」「文書の検索性を高めて査察対応をスムーズにしたいのか」「文書の版管理や承認プロセスを電子化したいのか」によって、選ぶべきツールは異なります。 「QAI Generator」は、特に「文書作成とレビューの時間を大幅に削減したい」という需要に強いツールですが、ご要望に合わせて様式をカスタマイズすることを前提としており、幅広いニーズに対応することができます。 製薬AI DX無料相談はこちら サポート体制と専門知識の有無 GMP文書は専門性が高く、業界特有の要件が多数存在します。そのため、ツールを提供するベンダーが製薬業界やGMPの業務プロセスを深く理解しているかどうかが、導入成功の鍵を握ります。万が一トラブルが起きた際や、運用方法に悩んだ際に、専門知識を持った担当者による手厚いサポートを受けられるかを確認しましょう。 弊社EQUESは製薬分野に特に強みを持っており、またAI専門家集団がお客様の困りごとに寄り添うサービス(AIDX寺子屋)も展開しておりますので、導入後も安心してご相談いただけます。 まとめ 今回は、医薬品の品質保証の要である「GMP文書」について、その基本から管理上の課題、そしてAIによる解決策までをご紹介しました。 GMP文書とは、GMP省令に基づき、医薬品の品質を保証する仕組みと実行を証明する文書群です。「製品標準書」「基準書」「手順書」「記録書」など多様な種類があります。GMP文書の管理は、法律で定められた義務であると同時に、多くの企業にとって大きな負担となっている現実があります。従来の紙や手作業による管理では、作成・レビューの時間、ヒューマンエラー、査察対応の非効率性といった課題がありました。AIを活用した「QAI Generator」のようなツールは、これらの課題解決に有効です。簡単な質問に答えるだけでAIが文書を自動作成します。実際の導入例では、作成時間が5割、レビュー時間が7割以上も短縮されています。 もし、貴社がGMP文書の作成・管理に課題を感じていらっしゃるなら、AIの力を活用してみませんか。 弊社(株式会社EQUES)は、製薬分野に強いAI専門家集団 として、貴社の業務効率化を全力でサポートします。ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。 製薬AI DX無料相談はこちら